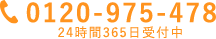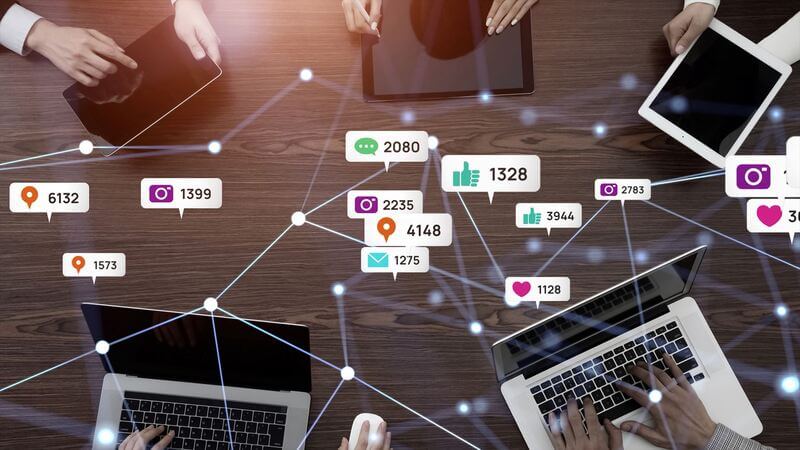映像制作・動画制作のコラム
2018年11月8日
動画制作で企画書を作るにはどうすれば良い?企画書作成のポイント
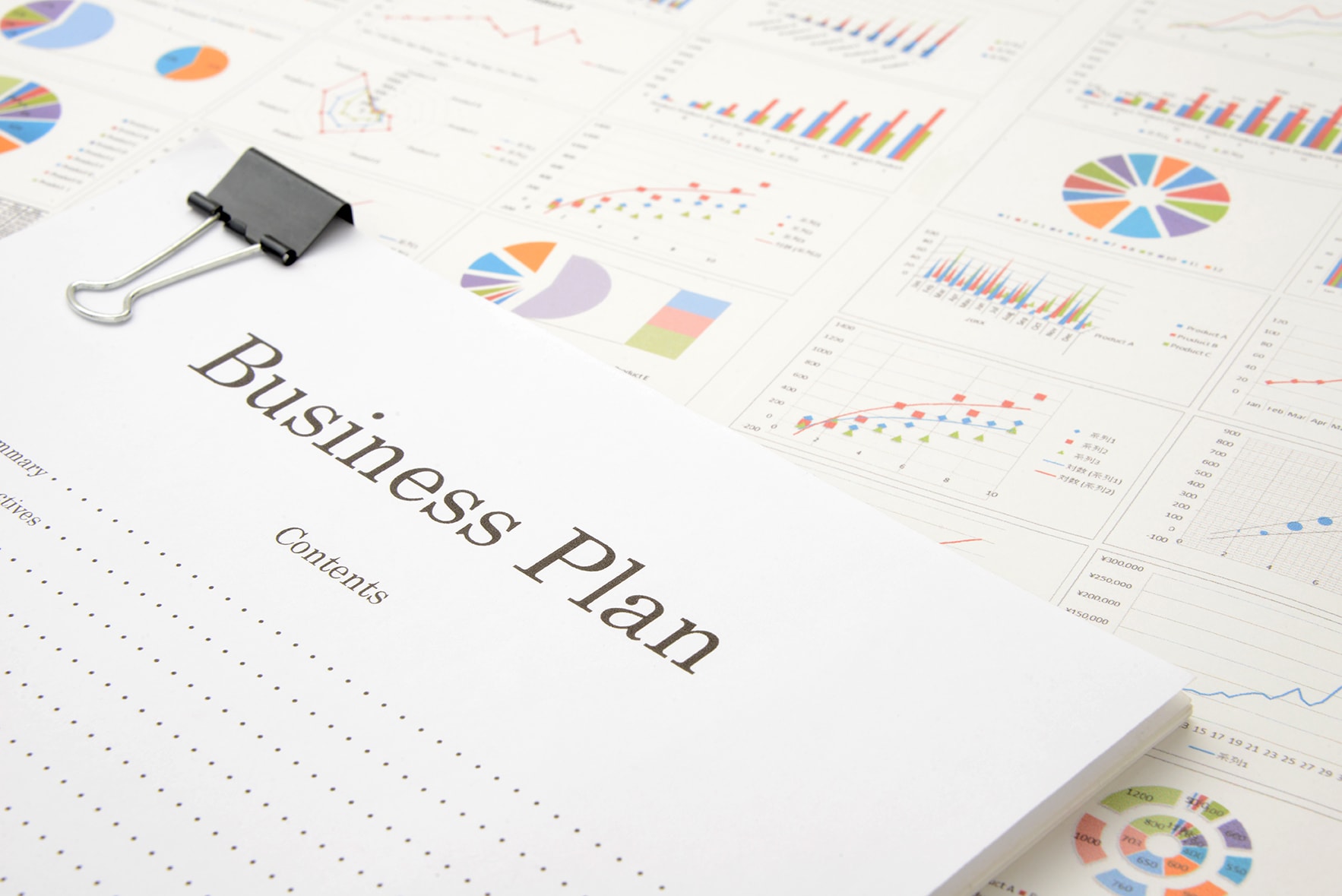
動画制作の工程において最も重要とも言えるのが企画書の制作です。企画書は、チームで動画を制作する際の意思統一のために有効であり、また、適当なスケジュールやコストを見積もるためにも必要です。そのため、例えばアイディアが素晴らしくても社内の経営層やクライアントに企画書でうまく伝えられなければ動画制作を進めることができないケースも多々あります。
本記事では、動画制作を効率的に進めるために不可欠な企画書の作り方やポイントについてわかりやすく解説します。
目次
動画制作の企画書に必要な3つの要素
まずはじめに、動画制作の企画書を作成する上で欠かせない3つの要素を紹介します。
動画の目的
まずは動画を制作することで何をしたいのか、どんな効果を生み、どんな結果を出したいのかについて明確にすることが大切です。代表的なものだと「自社の商品の認知度を上げたい」「自社サービスの売り上げを伸ばしたい」「ブランドイメージを良くしたい」などが挙げられ、このような明確な目的が企画書の段階で提示されていれば、動画制作に携わる全員が同じ方向に向かって進むことができます。
動画の目的を設定する際に一つ注意したいのが、「認知」と「購入」を同時に設定してしまうことです。認知が目的となる場合には、商品名を強調したりユニークな演出で拡散を狙う動画が有効ですが、購入が目的の場合には商品の特徴やメリット、購入したくなるようなキャンペーンの告知などを具体的に訴求する必要があります。「認知」と「購入」の目的を同じ動画に詰め込んでしまうと散漫な印象となり、視聴者は困惑してしまいがちなので目的は一つに絞ることが得策です。
動画のターゲット
動画制作の企画書には、ターゲット=「動画を視聴してほしい人物像」も細かく示します。この時に、年齢や性別、職業、住んでいる地域、家族構成、年収など、想定される人物像の詳細を挙げ、ターゲットを絞ることが大切です。動画制作を検討する企業がまずターゲットとして設定するのは「新規顧客」ですが、そのままでは訴求のポイント、共感を得やすい伝え方、向いている配信媒体が決められません。そのため、例えば30代の女性がターゲットの場合、仕事の忙しい人には時短をアピールし、主婦であれば家族全員で使える安心感や価格の安さなどを訴求するなど、動画の方向性が変わります。このようにターゲットとする人物像が詳細であればあるほど、戦力が立てやすくなるのです。
動画の数値目標
動画の目的を達成するためには、KPIを設定することが重要です。念のため解説しておくと、KPIとは認知・検討・行動といった目的(KGI)の達成度を計るための定量的な指標のことです。 動画広告には、再生回数や視聴完了率、クリック数など、さまざまな計測項目や指標が存在し、ここではその具体的な目標数値の設定を意味します。KPIの数値を設定していない場合には、動画を観たことによって増えた自社サービスのファンの数に関係なく、なんとなく目的を達成したことになってしまいます。具体的な数値目標を掲げていれば、より記憶に残る演出や構成を検討し、効果を考えながら動画制作を進めることができます。
動画制作の企画書を作成するときの具体的なポイントを3つピックアップ
次に上記の要素を踏まえた上で、実際に企画書を作成するときの具体的なポイントを紹介します。
企画書のフォーマットにとらわれない
初めて企画書を作る方は、どんなフォーマットにすればいいのかを気にしてしまうかもしれません。また、企業によっては企画書のフォーマットが定められているケースもあります。しかし基本的に形式は気にする必要はなく、重要なのは中身であることを念頭におきましょう。パワーポイントやグーグルスライドなど、とにかく見やすくわかりやすければ問題ありません。そして動画の企画書には、できるだけ再生数や視聴完了率、広告のクリック率など、数字を盛り込むことが有効です。動画は作ることがゴールなってしまいがちですが、重要なのは目標の達成です。目的や目標をは明確にし、企画書を見返したときに数値的な目標が達成できたかどうかを判断できる内容にしましょう。
動画の掲載先をあらかじめ設定する
「動画の掲載先の見極め」も重要なポイントです。動画の掲載先は、自社サイトをはじめ、SNS、動画共有プラットフォームど多岐に渡り、それぞれ公開できる動画の規格やサイズ、視聴者に好まれる尺などが異なり、バリエーションが豊富です。また掲載先によって視聴者層も異なるため、ターゲットと親和性の高いプラットフォームを選ぶことも重要です。ターゲットの生活スタイルから、動画を視聴しやすい時間帯を分析するなど事前のリサーチを踏まえ、企画書の段階で動画の掲載先を設定することが後のスムーズな制作につながります。
動画のビジュアルイメージを具体化する
動画の企画書では文字情報に加えて、企画段階で絵コンテやイメージ画像なども作成するのがポイントです。視覚的に共有できる情報があれば、企画側と制作側の認識のズレを防止でき、また、シナリオを絵コンテに落とし込むことで、撮影の構図や画角、必要な素材、強調したいシーンなどがより具体化し、実際の撮影もスムーズに進められます。
関連記事:映像制作には必須!絵コンテの作り方やポイントをわかりやすく解説
初めての映像制作の方にも、ご不安なくご利用いただけるよう制作の流れやご活用方法まで、
丁寧にご案内させていただきます。お客様の映像制作のゴールを達成するため、
企画〜撮影、完成まで専任チームが伴走いたします。
動画制作の企画書を作る4ステップ
動画の目的やターゲット、掲載先の設定
まずは動画の根幹となる目的を定め、ターゲット像を挙げ、ターゲット像の行動パターンなどを参照しながら動画の掲載先を設定します。
メッセージ・コンセプトの設定
ターゲットや動画のゴールから逆算し、目的を達成するにはどんなメッセージが最適なのかを考えます。メッセージを決めるポイントは、自社の商品・サービスの強み、競合と差別化できる点を熟知することです。またターゲットの趣味・趣向を理解するために、アンケートの実施や口コミサイトやSNSでリサーチなど、市場調査を行うことも有効です。
動画の尺と表現方法の設定
続いて動画の尺と表現方法を検討します。尺を設定するには掲載先のフォーマットをまず参照します。また、動画の長さは制作費に直結するので、予算を考慮して尺が設定されるケースもあります。動画の尺によって、動画の構成や表現方法が変わります。尺が短い動画なら、商品の特徴やメリットを直接的に訴求する、逆にある程度の長さがあれば悩みや課題などを前面に出し共感を促す構成にするなど戦略が変わります。
絵コンテや簡単なビジュアル資料を制作する
企画書の最終工程は、簡単な絵コンテの制作です。絵コンテとは、イラストやイメージ画像、内容、セリフやナレーション、尺、効果音などを記した構成案です。最初から細かく制作する必要はありませんが、動画制作に携わる人にどんな動画になるのかイメージを共有するための資料として制作します。
Shibuya Movieなら企画書作成から対応可能!
動画の企画書はハイクオリティーの動画を制作するために必要不可欠であり、企画書段階での精度が動画の仕上がりに大きく影響します。今回紹介したポイントを押さえることで、効果的な企画書を作成し、訴求力のある動画広告制作を目指すことができます。しかし、企業ブランディングに特化した動画のように特に高品質なものとなると、社内制作では限界がある場合がほとんどです。高いクオリティを求める場合は、動画制作会社に依頼し、企画書の段階からプロにお願いするのもひとつの方法です。
Shibuya Movieなら動画の目的や目標に応じて企画書から対応し、クオリティーの高い動画制作を実現します。是非企画書を含めた動画制作のご依頼は、Shibuya Movieまでお気軽にご相談ください。
初めての映像制作の方にも、ご不安なくご利用いただけるよう制作の流れやご活用方法まで、
丁寧にご案内させていただきます。お客様の映像制作のゴールを達成するため、
企画〜撮影、完成まで専任チームが伴走いたします。