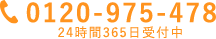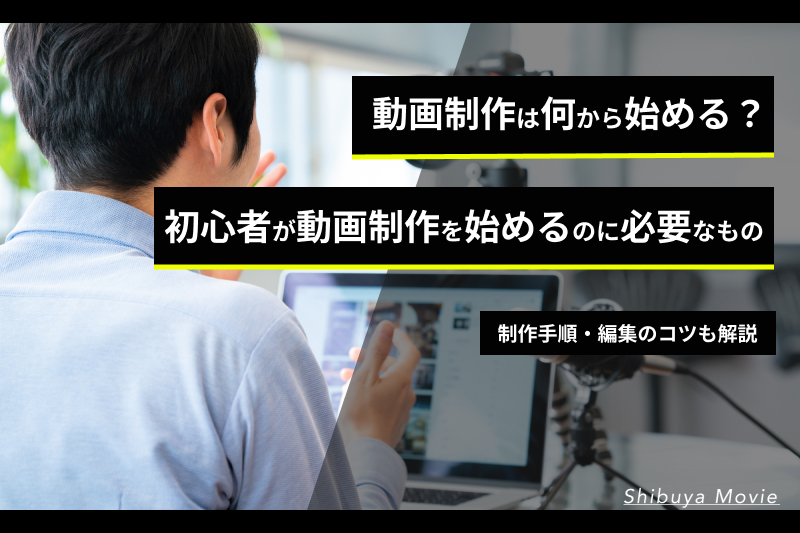映像制作・動画制作のコラム
2023年9月6日 最終更新日:2025年8月14日
マニュアル動画の作り方とは?メリット・デメリットと実際の作り方について映像のプロが解説

近年はペーパーレス化の進展やタブレット端末の普及に伴い、従来の紙マニュアルに代わる手段として、マニュアル動画を作成する企業が増えています。こうした背景もあり、商品説明や社員教育にかかるコストを削減すべく、マニュアル動画を作成したいと考えている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、マニュアル動画の活用シーンやメリット・デメリットをわかりやすく解説します。さらに、実際の作成手順や、質の高い動画を作るためのポイントも丁寧にご紹介。さいごには、参考になる事例も掲載しています。
「興味はあるけれど、まだ手をつけられていない」「何から始めればいいのかわからない」という方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
目次
マニュアル動画とは
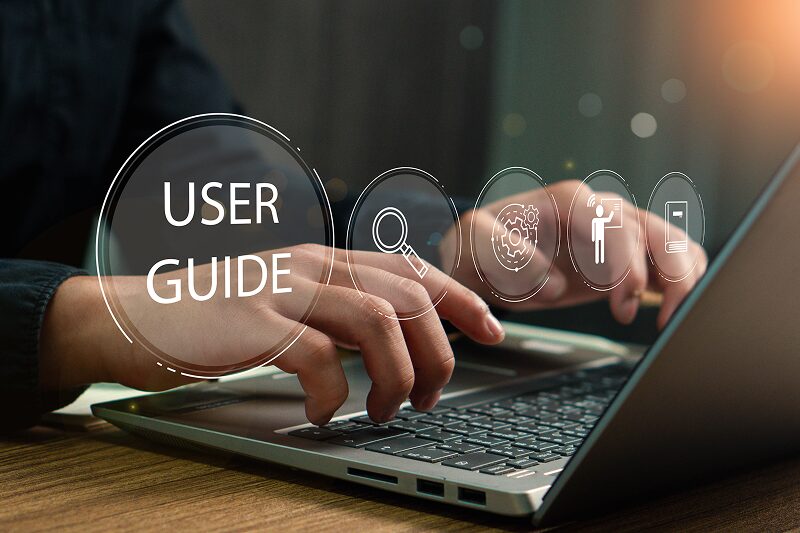
マニュアル動画とは、業務手順や製品の操作方法など、必要な情報を動画形式にまとめたものです。
マニュアル動画では、画像や文章で伝えにくい要素を視覚的に説明できるため、商品やサービスと連動させることでユーザビリティを高められます。また、社員の入れ替わりが多い企業や複数の店舗を展開する企業などでは、教育用のビジネスマニュアルを作成することで社員教育にかかるコストを削減できます。
マニュアル動画は大きく分けて、社外向けと社内向けの2種類があります。下記では社外向け・社内向けそれぞれの具体的な事例をご紹介します。
社外向けマニュアル動画
社外向けマニュアル動画とは、製品やサービスの取り扱い方法をわかりやすく説明する映像や、機械の操作手順を視覚的に解説する内容などが含まれます。
それでは具体的な事例を紹介していきます。
■正しい身だしなみ/株式会社リオ 本社
食品を取り扱う従業員の正しい身だしなみについて学習するマニュアル動画です。
作業する場合の制服や、着方の順番、装着不可のものなどを動画で説明することにより、理解しやすい内容となっています。
■ホテル・レストランスタッフ研修映像/あさのグループ
ホテルやレストラン、結婚式場のウェイターウェイトレスについての基礎技術を学ぶマニュアル動画です。
お皿の持ち方から料理の提供の仕方などを動画内で各セクションに分けて説明をしています。
■【stera】stera terminal取り扱い説明動画(全編)【三井住友カード公式】/三井住友カード【公式】
三井住友カードが提供するオールインワン決済端末「stera terminal」についての解説動画です。
本記事にて紹介している動画の中では一番長い動画となっていますが、
取扱時のすべての手順を細かく説明されており、チャプター分けもされているので分かりやすい動画となっています。
社内向けマニュアル動画
社内向けマニュアル動画には、新入社員向けの研修資料として活用される映像や、店舗運営の際に必要な製品の説明動画などが含まれます。
それでは具体的な事例を紹介していきます。
■【動画マニュアル】PCマイページ ユーザーマニュアル 全機能編【ジョブカン勤怠管理】/ジョブカン【jobcan】
勤怠管理システム「ジョブカン」のPCマイページのマニュアル動画になります。
出勤・打刻修正や休暇の申請方法などを実際のマイページ画面に沿ってスクロールしながら進んでいく為、
どなたでも理解がしやすい社内向けの動画となっています。
■ハンディーターミナル基本的な使い方|東芝テック製オーダーエントリーシステム『OrderStar』編/春日井流通マシン
飲食店で使用されているハンディターミナルの基本的な使い方をまとめた動画です。
店舗スタッフ向け動画となっており、初出勤時などは必見の内容となっています。
マニュアル動画の活用シーン

マニュアル動画を活用できるシーンはおもに以下の4つが挙げられます。
それぞれ詳しく解説していきますので、イメージを膨らませてみましょう。
- ●製品のチュートリアル
- ●作業マニュアル
- ●営業マニュアル
- ●研修マニュアル
製品のチュートリアル
近年、製品やサービスの使い方を説明する「チュートリアル動画」の需要が急速に高まっています。
従来は紙媒体の取扱説明書が主流でしたが、動画によるチュートリアルは視覚的かつ直感的に理解できるため、ユーザーの習得スピードが格段に向上します。
特にスマートフォンやPCなどの操作が複雑な製品では、実際の動作を見ながら学べる動画形式が非常に有効です。
また、動画の導入はユーザビリティの向上だけでなく、顧客満足度の向上にも寄与します。
製品の使い方をスムーズに理解できることで、問い合わせ件数の削減や、製品への信頼感の醸成につながり、結果として顧客のLTV(顧客生涯価値)の向上も期待できます。
企業にとっては、動画を活用したチュートリアルは、サポートコストの削減とブランド価値の向上を両立できる有力な手段となっています。
作業マニュアル
業務手順を新入社員や異動者に効率よく伝える手段として、作業マニュアル動画の活用が広がっています。
従来の紙ベースの手順書では伝えきれなかった業務の流れや全体像も、動画なら視覚的にわかりやすく、短時間で理解を深めることが可能です。
実際の作業風景や操作手順を映像で示すことで、現場での動きや注意点も効率的に学習できるため、習得のスピードが向上します。
さらに、動画を導入することで指導担当者の負担を軽減できます。特に多拠点展開している企業では、統一された教育コンテンツとして活用することで、業務の標準化にも貢献します。
作業マニュアル動画は、現代の業務教育において欠かせないツールとなりつつあります。
営業マニュアル
営業職において、自社製品やサービスの魅力を的確に伝えるスキルは欠かせません。
そのノウハウを効率よく共有する手段として、営業マニュアル動画の活用が注目されています。
動画なら、セールストークの流れや提案のタイミング、顧客対応のポイントなどを実際のシーンを交えて伝えることができ、理解度が高まります。
企業が共有しているセールスプロセスを動画で展開することで、情報の浸透が早まり、営業力の底上げにつながります。
結果として、売上の拡大や顧客満足度の向上も期待できるでしょう。また、営業と同様に接客業においても、マニュアル動画は有効です。
店舗での対応や商品説明の仕方などを映像で示すことで、スタッフの教育を効率化し、サービス品質の均一化にも貢献します。
マニュアル動画の活用は、営業現場の即戦力を育てるための強力なツールとして、今後ますます重要性を増していくでしょう。
研修マニュアル
新入社員やアルバイト従業員への研修において、マニュアル動画は非常に有効なツールとして活用されています。
従来の紙資料や対面指導では伝えづらかった業務の流れや注意点も、動画なら視覚的にわかりやすく、短時間で効率的に習得できます。
特に初期研修では、繰り返し視聴できる動画コンテンツが、学習の定着を促し、指導者の負担軽減にもつながります。
また、動画による研修マニュアルは、フランチャイズ店舗など多拠点での運営にも適しており、教育内容の標準化を図るうえで非常に効果的です。
接客対応やレジ操作、衛生管理など、業務ごとに分かりやすく整理された動画は、現場での即戦力育成に貢献します。
企業にとっては、研修の質を高めながらコストを抑える手段として、研修動画マニュアルの導入がますます重要になっています。
マニュアル動画を作るメリット

マニュアル動画を導入することで得られる、5つの主なメリットをご紹介します。
一つずつ詳しく見ていきましょう。
- ●自社の資産になる
- ●作業コストを圧縮できる
- ●営業資料としても使える
- ●紙媒体よりもわかりやすい
- ●言語の壁を越えて情報を伝えられる
自社の資産になる
マニュアル動画は一度作れば二度目以降はコストをかけることなくさまざまな場面で活用でき、資産としての価値を見込めます。
作成すると、紙に印刷したマニュアルに比べても、印刷代などのコストがかかりません。長期的に活用できる点や、容易に再配布・掲載ができる点を考慮すると、作成するメリットは大きいといえるでしょう。
作業コストを圧縮できる
動画は文章の5,000倍の情報量を伝えられるといわれており、1分の間に動画で伝えられる情報量はWebサイトの約3,600ページ分に匹敵する計算です。
社内外向けのマニュアルを動画化することで、口頭やテキストで説明を行なうよりもはるかに少ないコストで情報を伝えられます。
そのため、作業コストを削減したい場合は、マニュアルの動画化を検討するとよいでしょう。
営業資料としても使える
自社の商品やサービスを営業する際、マニュアル動画を活用することで操作感などをイメージしてもらいやすくなります。
マニュアル動画を動画視聴サイトやクラウドなどにアップしておくと、時間や場所に関係なく視聴できるため、取り引き先へ何度も足を運ぶ必要がありません。
社外での使用や持ち出しが難しい商品についても、マニュアル動画の活用で説得力のあるプレゼンテーションを行なえるでしょう。
紙媒体よりもわかりやすい
マニュアル動画の場合、複雑な操作や作業をともなうものでも、視覚と聴覚の両方でわかりやすく説明できるのが強みです。
実際の操作や作業を、疑似体験のように人の動きや音声をともなった映像として見られるなど、紙媒体に比べ、習熟度や理解度が高くなる点もマニュアル動画のメリットでしょう。
自社向けや社外問わず、分かりやすいマニュアル動画の制作ならShibuya Movieにお任せください!
どんな人にでも分かりやすいマニュアル動画の制作をサポートさせていただきます。
初めての映像制作の方にも、ご不安なくご利用いただけるよう制作の流れやご活用方法まで、
丁寧にご案内させていただきます。お客様の映像制作のゴールを達成するため、
企画〜撮影、完成まで専任チームが伴走いたします。
言語の壁を越えて情報を伝えられる
多様な国籍の人材を受け入れる現場では、言語の違いが業務理解の障壁となることがあります。そこで有効なのが、マニュアル動画の活用です。
映像を通じて作業手順や注意点を視覚的に伝えることで、言葉に頼らず直感的に理解を促すことができます。
さらに字幕を多言語で表示すれば、母語での補足も可能となり、理解度が格段に向上します。
動画は一度作成すれば繰り返し利用でき、教育コストの削減にもつながるため、外国人労働者の受け入れを進める企業にとって非常に有益なツールです。
マニュアル動画を作る際のデメリット
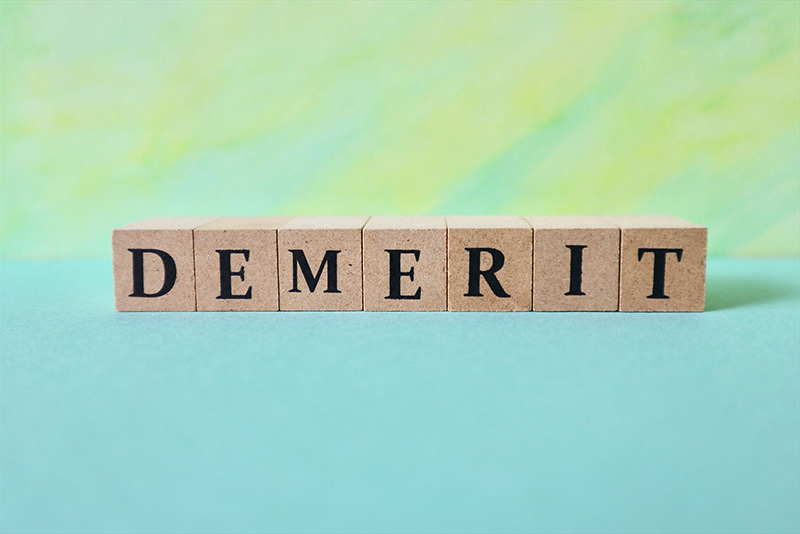
マニュアル動画は紙媒体に比べてメリットが多いため、多くの企業で採用されているコンテンツです。しかし、作成するうえでは紙媒体にない以下のようなデメリットもあります。
内容の更新が大変
マニュアル動画の場合、どんなに細かな内容の更新であっても、マニュアルを変更する際は動画の作り直しや編集をしなければいけないのがデメリットです。
定期的に改修を行なう商品やサービスの場合、改修のたびにマニュアル動画の更新が必要になるため、作業の負担を感じやすいでしょう。SNSや動画視聴サイトにマニュアルをアップロードしている場合は、新しいものを再アップロードする作業や、顧客や社員への周知も必要です。
こうした負担を少しでも軽減するためには、動画での説明が必要ない部分は静止画を使うなどして、改修のたびに更新しなくて済むような構成を考えることが大切です。
部分的な確認が難しい
部分的な確認や修正を行なう際、紙の資料はページごとに修正や差し替えが可能ですが、動画はピンポイントで再生することが難しい場合があります。
動画の内容やストーリーによっては、部分的な修正にともなって動画全体の構成から作り直さなければいけないケースもあるでしょう。こうした動画の特性から、マニュアル動画を作る際は内容やテーマに合わせて動画を短く区切り、長編の構成にしないことが大切です。
特に、情報量が多い場合は動画を短く区切って数本に分けるとよいでしょう。1本の長い動画に比べ、視聴者の集中力も持続しやすくなります。
マニュアル動画の作り方
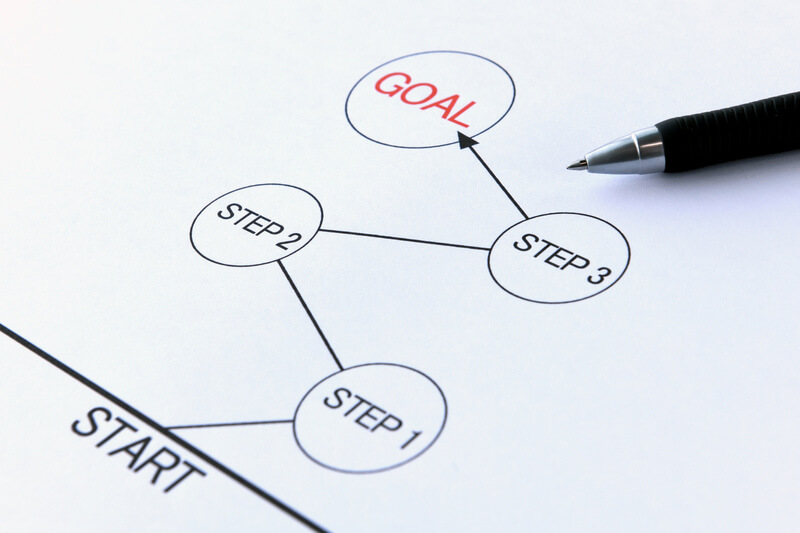
マニュアル動画制作の基本的な5つフローと、各ステップのポイントを解説します。
- 1.動画を作る目的を定義する
- 2.企画・構成を作成する
- 3.動画の撮影を行なう
- 4.動画の編集・修正を行なう
- 5.動画を公開する
1.動画を作る目的を定義する
まず、マニュアル動画を作る目的を明確にし、ターゲットや盛り込む内容を決めていきます。なぜマニュアル動画が必要なのか、どのような人にマニュアル動画を届けたいか、どのような内容なら視聴者が理解しやすいかといった点を深掘りしていきましょう。
マニュアル動画は、最終的に視聴者が理解しやすい内容にまとまっていることが大切です。目的やターゲット、内容が定まっていれば、次のステップ(企画・構成)もスムーズに進められるでしょう。
2.企画・構成を作成する
前のステップで決めた内容に沿って構成案を作成し、動画全体の流れや細かな撮影スケジュールを決めていきます。ターゲットが求めている情報が盛り込まれているか、無理なく撮影できるスケジュールになっているか確認しましょう。
台本が必要な場合は企画・構成の段階で作成します。撮影機材や撮影場所の確保、モデルの起用などもこの段階で済ませておくことで、撮影時の時間ロスを防げます。
3.動画の撮影を行なう
構成案に沿って動画の撮影を行ないます。撮影時は、同じシーンをさまざまなアングル(角度)や方向、パターンで撮影しておくことで動画素材が充実し、よりクオリティの高い動画に仕上げることができます。
撮影パターンが少ないと、撮りなおしが必要となるリスクもあるため注意しましょう。
4.動画の編集・修正を行なう
撮影した動画を編集します。不要なシーンのカットやトリミングを行なって必要な映像のみをつなぎ合わせ、強調させたい部分にテロップやナレーションを入れていきます。
必要に応じてBGMや効果音、図やアニメーションなどを入れることで動画のクオリティが上がり、より見やすいマニュアル動画になるでしょう。
近年は電車やバス移動などの隙間時間を活用して動画を視聴する人も多いため、そのような層に向けたマニュアル動画では字幕を入れるのも効果的です。
編集時に足りない動画素材があれば、撮りなおしを検討しましょう。
5.動画を公開する
完成した動画を公開します。社外向けマニュアル動画の場合、ホームページやSNS、動画視聴サイトなどにアップロードしたり、動画URLをメールマガジンで送信したりして周知させましょう。
社内向けマニュアル動画の場合は、社内のWebサイトや共有フォルダにアップロードしたり、社員に動画URLを配布したりして、必要に応じて視聴指示を出しましょう。
マニュアル動画の質を上げるコツ

マニュアル動画の質を上げるうえで気を付けたい、制作のコツを8つ紹介します。
これからマニュアル動画を制作しようと考えている方はぜひ参考にしてくださいね。
- 内容にメリハリを付ける
- 情報の抜け漏れをチェックする
- 集中して見れる長さを意識する
- 撮影の環境や角度に配慮する
- 必要に応じて静止画を活用する
- テロップやナレーションを効果的に使う
- 活用シーンごとのポイントを確認する
- 管理方法にも気を付ける
内容にメリハリを付ける
マニュアル動画は、視聴者に情報を正確に伝えるための有効な手段ですが、内容が単調だと途中で飽きられてしまうことも少なくありません。そこで重要なのが「メリハリ」です。
たとえば、重要なポイントではテロップや音声で強調したり、場面転換や図解を活用することで、視聴者の注意を引きつけることができます。また、説明のテンポや話し方に変化をつけることで、理解しやすく印象に残る動画になります。
単なる情報の羅列ではなく、視聴者の視点に立って構成を工夫することが、質の高いマニュアル動画を作るポイントです。
情報の抜け漏れをチェックする
マニュアル動画を制作する際に最も重要なのは、伝えるべき情報を正確かつ過不足なく盛り込むことです。
まずは紙のマニュアルや既存の資料をベースに、動画で補足すべき作業映像や説明箇所を洗い出しましょう。特に、視聴者がつまずきやすい工程や注意点は、映像とナレーションで丁寧に補強することが求められます。
一方で、情報を詰め込みすぎると視聴体験が損なわれ、かえって理解を妨げることもあります。そのため、内容は「必要十分」を意識し、視聴者の立場で情報の取捨選択を行うことが大切です。
制作後には第三者の視点でチェックを行い、抜け漏れや過剰な説明がないかを確認することで、より完成度の高いマニュアル動画に仕上がります。
集中して見れる長さを意識する
マニュアル動画の目的は、視聴者に必要な情報を確実に届けることです。
しかし、動画が長すぎると集中力が途切れ、最後まで見てもらえない可能性があります。
そこで意識したいのが「視聴に適した長さ」です。一般的には1〜3分程度が理想とされ、短時間で要点を押さえた構成が効果的です。また、1つの動画に複数のテーマを詰め込むのではなく、1テーマにつき1動画とすることで、視聴者が知りたい情報にすぐアクセスできるようになります。
動画を小分けにすることで、検索性も高まり、学習効率も向上します。視聴者の集中力と利便性を考慮した設計が、マニュアル動画の質を大きく左右するのです。
撮影の環境や角度に配慮する
マニュアル動画の見やすさは、撮影環境によって大きく左右されます。
まず、対象物がはっきりと映るように、明るい場所で撮影することが基本です。
自然光だけでは不十分な場合は、スタンド照明などを活用して、影や暗部を減らしましょう。
また、同じ作業でもアングルを変えたり、手元を寄りで撮影することで、視聴者にとって理解しやすい映像になります。特に細かい作業や注意点がある場面では、複数の角度からの映像が効果的です。
さらに、撮影時にシーン名を書いたホワイトボードなどを画面に映しておくと、編集作業がスムーズになり、動画の構成も整理しやすくなります。
視認性と編集効率の両面から、撮影環境と角度への配慮は欠かせないポイントです。
必要に応じて静止画を活用する
マニュアル動画を制作する際、映像だけに頼るのではなく、静止画を効果的に取り入れることで、より伝わりやすいコンテンツに仕上がります。
静止画の最大の利点は、視聴者が情報をじっくり確認できる点と、強調したい部分を明確に示せる点です。
たとえば、複雑な手順や細かい部品の構造などは、動画よりも静止画のほうが理解しやすい場合があります。
動画と静止画、それぞれの特性を理解し、場面に応じて使い分けることで、視聴者にとって親切で実用的なマニュアル動画を作ることができます。
テロップやナレーションを効果的に使う
マニュアル動画では、視聴者に重要な情報を的確に伝えるために、テロップやナレーションの活用が欠かせません。
特に強調したいポイントや補足説明には、テロップを入れることで視覚的に情報を補強できます。
ただし、テロップを多用しすぎると画面が煩雑になり、作業の様子が見づらくなる恐れもあります。
そこで、ナレーションを併用することで、耳から情報を伝えつつ、映像の動きに集中できる構成が理想的です。
視覚と聴覚のバランスを意識しながら、場面に応じて使い分けることで、より理解しやすく質の高いマニュアル動画が完成します。
活用シーンごとのポイントを確認する
マニュアル動画を効果的に制作するためには、活用されるシーンごとの目的や視聴者のニーズをしっかりと把握することが重要です。
たとえば、製品のチュートリアル動画では、実際に製品を操作する様子を映しながら、使い方や注意点を具体的に示すことで、視聴者が自分で使う際のイメージを持ちやすくなります。
一方、社内研修用のマニュアル動画では、業務の基本的な流れやルールなど、知っていて当然と思われる内容でも丁寧に説明することが求められます。
視聴者の前提知識や目的に応じて、どこまで詳しく説明するかを調整することで、理解しやすく実用的な動画になります。
データの保存管理方法にも気を付ける
せっかく質の高い動画を作っても、保管データの保存先がバラバラだったり、古い情報データと更新済みのデータが混在していると、視聴者が必要な情報にたどり着けず、活用されにくくなります。
動画の保存先は社内で統一し、検索しやすいフォルダ構成やタイトル付けを工夫することが重要です。
また、内容を更新した際には古い動画を削除するか、更新日を明記するなどして、常に最新の情報が伝わるようにしましょう。
管理体制を整えることで、マニュアル動画は継続的に活用される有益なツールになります。
効率の良いマニュアル動画の作り方

マニュアル動画を効率よく作るには、「制作会社に依頼する方法」と「専用ソフトを使って自分で作る方法」の2つがあります。
ここでは、目的や状況に合わせて選ぶ際のポイントについて解説します。
制作会社に依頼する
クオリティの高い動画を自社で一から制作するのは、時間も労力もかかるもの。
そこでおすすめなのが、専門の制作会社に外注する方法です。
外注先を選ぶ際は、過去の制作実績や提案力、費用感などを総合的に比較検討し、自社の目的や予算に合ったパートナーを見つけることが重要です。
多少コストがかかっても、長期的に見れば高品質な動画は業務の生産性向上に貢献します。
「コストはかかっても、質の高い動画を作りたい」そんな企業におすすめなのがShibuya Movieです。
丁寧なヒアリングと柔軟な提案で、目的に合った最適なマニュアル動画を制作します。
動画制作に不安がある方も、まずはお気軽にご相談ください。
専用ソフトを使う
マニュアル動画を効率よく制作するには、「専用ソフトを使う」ことが非常に有効です。
これらのソフトは初心者でも直感的に操作できるよう設計されており、一度基本的な使い方を覚えれば、作業時間を大幅に短縮できます。
録画、編集、ナレーションの追加など、動画制作に必要な機能が一通り揃っているため、複数のツールを使い分ける手間も省けます。
ソフトを選ぶ際には、搭載されている機能の充実度が自分の目的やスキルレベルに合っているかを確認することが大切です。
また、操作性やユーザーサポートの体制も重要なポイントです。業務で使用する場合は、トラブル時に迅速な対応が受けられるかどうかも確認しておくとよいでしょう。
目的に合った専用ソフトを選び、使いこなすことで、効率的かつ高品質なマニュアル動画の制作が可能になります。
マニュアル動画の制作事例
さいごに、実際のマニュアル動画の事例2選を紹介します。
株式会社ロマック様/商品紹介編
本事例は、株式会社ロマック様の商品を紹介するために制作された、マニュアル動画形式の商品紹介映像です。視聴者が「自分でもできそう」と感じられるよう、実演を中心に構成されており、購入前・購入後の両方で活用できる実用的な映像となっています。
1. 視覚的にわかりやすい組み立て手順の解説
動画では、商品の基礎部分から柱立てまで、一連の施工手順を丁寧に紹介。ナレーションやテロップを最小限に抑え、映像だけで理解できる構成が特徴です。
2. 「女性ひとりでもできる」を証明するリアルな演出
実際に女性キャストが組み立てを行うことで、「誰でも簡単に扱える」ことを視覚的に証明しつつ、マニュアルとしての信頼性を高めると同時に、商品への安心感と親しみやすさを提供します。
3. 購入前・購入後の両方に機能するハイブリッド型
この動画は、商品紹介とマニュアルの両方の役割を果たす構成になっています。
購入前:商品の魅力と使いやすさを訴求
購入後:組み立て手順のガイドとして活用
視覚的にも理解しやすい商品紹介が、販促と組立説明書の両立を可能にしています。
株式会社プロテック様/商品紹介映像
本事例は、株式会社プロテック様のリニューアル商品を紹介するために制作された、マニュアル動画形式の商品紹介映像です。店頭で商品を手に取りながら視聴できるよう設計されており、購入前の理解促進と購入後の使用サポートを両立する映像となっています。
1. 実際の使用シーンを交えたマニュアル構成
ホームセンターのDVDプレーヤーで映像を流すことを前提に、商品の利用シーンを再現しながら、各機能や特性をポイントごとに紹介。視覚的に理解しやすく、説明書の代わりとしても機能する構成です。
2. 商品の進化を伝えるストーリーテリング
既存商品からのリニューアル品であることを踏まえ、「何がどう進化したのか」を明確に伝える演出を採用。従来品との違いや改善点を映像で示すことで、購入意欲を高めます。
3. 店頭での補助ツールとしての活用
映像は、商品を手に取った瞬間に補足情報を提供するマニュアルツールとして活用可能。
購入前:商品の魅力と使い方を視覚的に伝える
購入後:使用方法の確認ツールとして機能
購入前後のあらゆるシーンで活躍する、実用性に優れたマニュアル動画です。
まとめ
マニュアル動画は、紙媒体に比べて多くの情報をわかりやすく伝えられるコンテンツです。作成や更新には一定のコストがかかりますが、情報資産として長期的に活用できることから費用対効果が高く、視聴する側の習熟スピードも速いといったメリットがあります。
Shibuya Movieでは、グラフィック・Web・動画を連携させたクロスメディアマーケティングで企業が抱える課題の解決をサポートしています。
社外向けのマニュアル動画を公開して顧客を増やしたい、社内向けのマニュアル動画で新人教育コストを軽減させたいなど、課題解決に向けたマニュアル動画作成を考えている方はぜひお気軽にShibuya Movieへご相談ください。
初めての映像制作の方にも、ご不安なくご利用いただけるよう制作の流れやご活用方法まで、
丁寧にご案内させていただきます。お客様の映像制作のゴールを達成するため、
企画〜撮影、完成まで専任チームが伴走いたします。