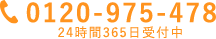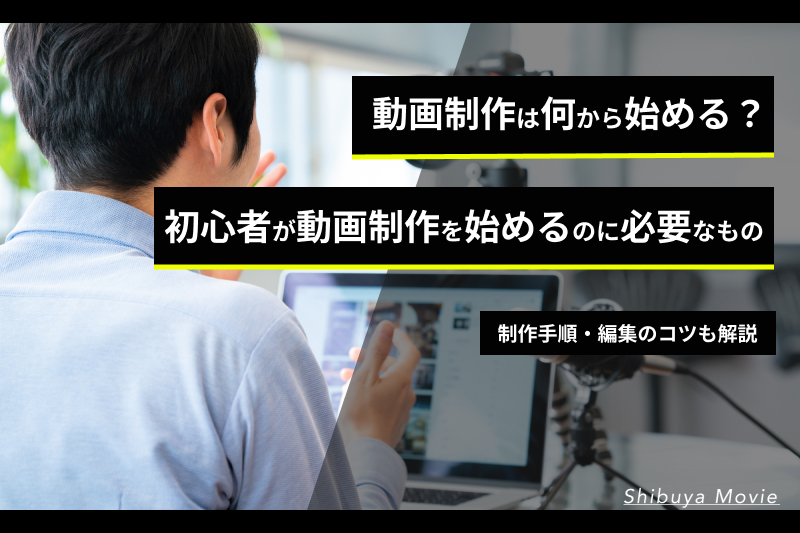映像制作・動画制作のコラム
2025年1月22日
士業が動画を制作するメリットとは?効果的な動画制作のための注意点も解説

近年、さまざまな業界で動画をビジネスに活用する場面が増えてきました。しかし、弁護士や税理士といった士業で動画を活用している方はまだ少数のようです。
効果的な動画を制作しうまく活用できればマーケティングに大いに役立つなど、多くのメリットがあります。また、同業他社との差別化にもなるでしょう。
そこで本記事では、士業が動画を制作するメリットや活用方法、制作時に気をつけたいポイントのほか、外注先としてどこに依頼すれば良いのかを解説します。
士業が動画を制作するメリット

ここでは、士業が動画を制作する6つのメリットを紹介します。
サービス内容をわかりやすく伝えられる
弁護士や税理士、司法書士といった士業が取り扱うサービスは、どれも専門性が高いため、一般の方からするとわかりにくいと思われがちです。
そもそもどのようなサービスを提供しているのかわからないと、依頼することができません。
動画であれば、文章だけでは伝えきれない複雑な情報を、音声やビジュアル、動きを使ってやさしくわかりやすく説明できます。
映像と音声を組み合わせて説明することで、記憶にも残り、理解が深まりやすくなるでしょう。
名前を覚えてもらえる
士業で動画を活用している方はまだ少数です。そのため、動画を制作し、SNSで公開したり広告として出稿したりすることで、さまざまな人に顔や名前を覚えてもらいやすくなります。
たまたま動画を見た人に、すぐに問い合わせてもらえるわけではないかもしれません。
しかし、名前を知ってもらうことで、いざ士業が必要になった際に「動画で見たあの人に頼んでみよう」と新規顧客を獲得するきっかけになることがあるでしょう。
人柄を伝えることができる
一般の方が士業に仕事を依頼する際、サービス内容で選ぶことももちろんありますが、最終的には人柄を重視して選ぶ方も多いようです。
しかし、事務所ホームページに簡単なプロフィールと写真を載せているだけでは、人柄が十分には伝わりません。
多くの方にとって士業は馴染み深いものではなく、依頼する方が不安を感じてしまうこともあるでしょう。
動画で顔を出し、話し方や雰囲気を見てもらうことによって、人柄をアピールすることができます。
誠実さや業務に取り組む姿勢を知ってもらえば、「この人なら親身になってくれそう」と安心してもらえるため、結果的に依頼につながることもあります。
何度も利用できて資産として残る
「動画を作るのは大変そうだし、時間がかかってもったいない」と思う方もいるかもしれません。しかし、動画は一度作ってしまえば資産として残り、さまざまな場面で何度も利用することができます。
例えば、事務所のホームページに載せる目的で制作した自己紹介動画は、講演会で講師を務めるときにも利用できます。
また、サービス内容を説明した動画を制作し、それを依頼者の方に見てもらうことで、何度も同じことを説明する手間が省けます。必要な情報の伝え忘れも防ぐことができるでしょう。
さらに、士業の専門知識を活かした生活に役立つコンテンツをYouTubeに投稿しておけば、それを見た方が問い合わせてくれる可能性もあります。
動画制作は手間がかかりますが、長い目で見ると効率的に集客できる資産となります。
伝えられる情報量が多い
動画は、文章や写真と比べて一度に伝えられる情報が非常に多いといわれています。具体的には、1分の動画で180万語分の情報を伝えることができます。
Webページに換算すると、3,600ページ分のテキストと同じくらいの情報ということですから、驚きです。
動画を活用すれば、短時間で伝えるべき情報を活字以上に多く伝えられます。説明が足りず齟齬が生じてしまうことも減るでしょう。
動画で情報収集する人が増えている
総務省情報通信政策研究所「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」によると、2014年にYouTubeを利用している人は全年代で65.1%でしたが、年々増え続け、2023年には87.8%となりました。
年齢別に2023年の結果を見ると、10代から40代のYouTube利用率は90%を超えており、50代も約87%、60代も約72%の人がYouTubeを利用しています。
情報収集に動画を利用する人は、今後も増加していくと考えられます。動画で発信することで、より多くの人にアプローチしやすくなるでしょう。
士業が動画を活用する6つの方法

ここからは、士業は動画をどのように活用できるのか、その具体的な方法を紹介します。
サービス内容の紹介
活用方法の一つは、自社がどのようなサービスに対応しているのか、具体的な内容を紹介することです。
同業他社にはない強みを説明したり、インタビュー形式でよく聞かれる質問に回答したりするのもおすすめです。
事務所のプロモーションや個人のプロフィールを紹介
士業にとっつきにくく堅苦しいイメージを持っており、相談をためらっている方も多くいます。
そこで、事務所で働いている普段の姿や、話し方の雰囲気などを動画で見せて、堅いイメージをやわらげ、士業を身近に感じてもらうのも活用方法の一つです。
個人のプロフィールも、経歴や職歴と顔写真だけではどのような人か想像が付きにくいものです。
仕事に真摯に取り組む姿を動画で映したり、仕事に対する思いを語ったドキュメンタリー動画を制作したりすることで、誠実な人柄をアピールできます。
事務所のプロモーション動画やプロフィール動画は、そのままリクルートにも活用可能です。
セミナーを動画で配信
士業の重要な集客方法の一つにセミナーがありますが、毎回会場を押さえるのは面倒ですし、費用もかかります。セミナーを動画で配信すれば、会場準備の手間や費用を削減できます。
遠方に住んでおり、これまでセミナーになかなか参加できなかった人も、交通費の負担がないため気軽に受講できるようになるでしょう。
時間の都合でリアルタイムでの参加が難しい方も、あとで録画を確認できます。
YouTubeチャンネルでお役立ち情報を解説
YouTubeチャンネルを開設し、専門知識を活かしたコンテンツを制作するのもおすすめです。
例えば、一般の方には理解しにくい専門的な内容をわかりやすくかみ砕いて説明するコンテンツや、日常生活で知っておくと役立つ情報を紹介するコンテンツなどが挙げられます。
話題のニュースを専門家の視点で解説する動画も、多くの方に見てもらいやすいでしょう。
これらは、自分や事務所を直接アピールするというよりも、有益な情報で視聴者を集め、顔や名前を知ってもらうことが目的です。
顔や名前を広めることで、のちに士業が必要になった際に問い合わせてもらえる可能性が高まります。
一度制作した動画コンテンツは、制度や仕組みが変更にならない限り使えます。
何年も前に投稿した動画が問い合わせにつながる可能性もあるため、長期的な営業ツールとして利用できるのです。
士業とエンタメを組み合わせたコンテンツを配信
士業とエンタメを組み合わせ、情報を伝えるよりも楽しく見てもらうことを目的とした動画コンテンツを作るのもよいでしょう。
例えば「弁護士あるある」や「税理士が○○やってみた」などの堅苦しくなく気軽に見られる動画であれば、これまで士業にまったく興味がなかった方にも見てもらえる可能性が高まります。
TikTokやYouTubeのショート動画などで配信し、短時間で興味を持ってもらうことで見込み客を増やす目的です。
ただし、面白さや親しみやすさを重視しすぎて過激な発言をしたり、あまりに砕けた姿を見せたりすると士業としての信頼感や品位を損ない、逆効果となってしまうこともあるため注意してください。
動画広告を出稿する
YouTubeやTikTokなどに動画コンテンツを投稿しても、人気が出るまではなかなか視聴数が伸びず、成果が出ないこともあります。
また、情報を必要としている方に届かない場合もあるでしょう。
動画広告であれば、広告費を支払うことによって、士業を必要としているであろう方に絞ってアプローチすることが可能です。
ただ動画コンテンツを投稿するよりも、早く成果が出やすい手法です。
効果的な動画制作のために気を付けたいポイント

士業が動画を活用する例を紹介してきましたが、動画はただ作るだけでは十分な効果が出ないこともあります。
そこでここからは、効果的な動画制作のために気を付けたいポイントを紹介します。
ターゲットに見てもらえる動画を作る
せっかく時間をかけて動画を制作しても、見てもらえないと意味がありません。動画の目的やターゲットを決め、どのような動画が求められているか考えて企画を作りましょう。
既存の動画と同じ内容にならないよう、オリジナルの要素を入れて差別化するのがポイントです。
例えば、以下のような企画が考えられます。
- ●話題性のある情報を取り上げた動画
- ●ニーズはあるが世のなかにまだ存在していない動画
- ●既存のものより詳しくわかりやすい動画
何年も繰り返し使える動画を作る
流行の話題や時事問題について取り上げた動画は、短期間での視聴回数を稼ぎやすいというメリットがありますが、一定期間が過ぎると情報が古くなり、ほとんど視聴されなくなります。
流行を追いかけることは大事ですが、それだけでなく、何年も変わらずニーズが続きそうな動画も制作しておくことをおすすめします。
何年も視聴され続けている動画があれば、長期間安定して集客できますし、動画制作のコストも節約できるでしょう。
実写とアニメーションを効果的に使い分ける
動画には、大きく分けて実写動画とアニメーション動画があります。
それぞれ強みが違うため、目的や内容によって実写とアニメーションを使い分けましょう。
例えば、士業のイメージを良くして集客につなげたい場合は、事務所のようすや人柄をありのまま見せることができる実写動画が有効なことがあります。
また、難しいサービス内容をわかりやすく説明したい場合は、抽象的な概念を説明しやすいアニメーション動画が適していることが多いでしょう。
イメージダウンにつながる動画はNG
士業を身近に感じてもらうために、動画で親しみやすさをアピールすることは効果があります。
しかし、先ほども述べたように、あまりにも砕けすぎてしまうと、信頼性を失い、逆にイメージダウンになってしまうこともあるため、ちょうど良いバランスが大切です。
動画の内容も、視聴回数を伸ばしたいあまりに刺激が強すぎる内容にすると炎上して非難を浴びてしまうこともあるため、注意が必要です。
士業の動画制作はどこに依頼すべきか

「動画制作の知識や経験がない」「制作にかける時間が取れない」という方は、動画制作を行なう会社に依頼しましょう。
動画制作会社は多数ありますが、士業が動画制作を依頼するなら、以下のような会社がおすすめです。
士業の知識や実績がある会社に依頼する
士業にかかわる専門的な知識や経験をある程度持っているほうが、動画制作がスムーズに進みます。
士業の動画制作の実績がある会社や、士業の事務所で働いた経験があるスタッフがいる会社を選ぶことで、ポイントを押さえて効果的な動画を制作してもらえる可能性が高まります。
可能であれば、士業の動画制作の実績を見せてもらうことをおすすめします。
マーケティングもできる会社に依頼する
ただ動画を制作して終わりではなく、その後の運用やマーケティングまでワンストップでサポートしてくれる会社がおすすめです。
完成した動画をどのメディアで配信すべきか、また、動画広告として出稿する場合はどのような人をターゲットにすべきかなど、さまざまな戦略をしっかりと練ることで、作った動画の効果を最大限に発揮できるでしょう。
士業動画の制作事例の紹介

ここでは、Shibuya Movieがこれまでに制作した士業動画の一部を紹介します。
RSM清和監査法人様
RSM清和監査法人様のWebページへの掲載やWeb広告として出稿する目的で、公認会計士を採用するための動画を制作いたしました。
落ち着いたナレーションでRSM清和監査法人様ならではのさまざまな魅力を伝えます。また、理事長からの生の声も入れることで魅力がより伝わるようになっています。単調にならず見やすい動画にするために、オフィス内部だけでなく、屋外の映像やCGも取り入れています。
デロイトトーマツ税理士法人様
デロイトトーマツ税理士法人様のホームページに掲載するための人材採用動画を制作いたしました。
若手を含めた複数のスタッフが取材を受ける形式で自社に入って良かったことや、デロイトトーマツの魅力を伝える動画です。
美しいオフィスをシネマチックな映像で魅力的に映すことで、入社後に働く環境をイメージしやすくなっています。
まとめ
この記事では、士業が動画を活用するメリットや活用方法について解説しました。
士業で動画を活用している方はまだ少数です。そのため、効果的に動画を取り入れることで同業他社と差別化でき、集客や採用などさまざまなメリットを得られるでしょう。
士業の動画制作を外部に依頼する際は、士業の知識やマーケティングの知識を持った制作会社を選ぶのがおすすめです。本記事を参考に、動画制作をぜひご検討ください。