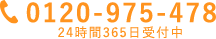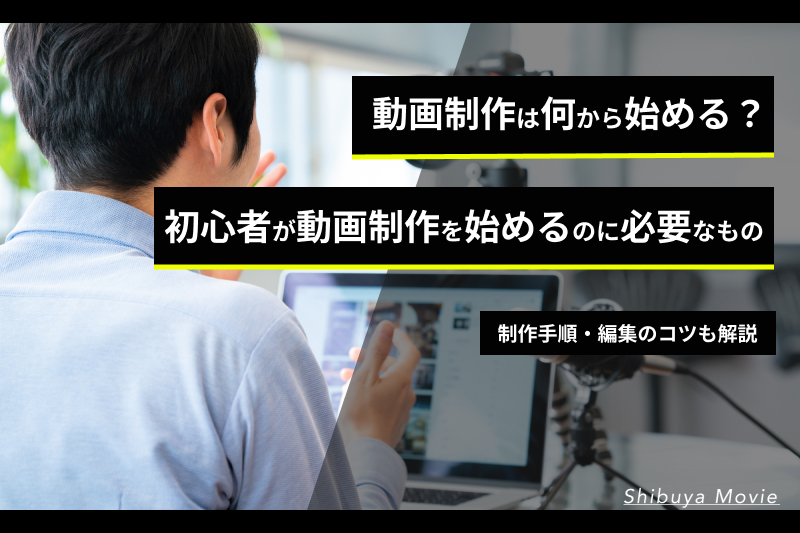映像制作・動画制作のコラム
2021年4月16日 最終更新日:2025年8月14日
啓蒙動画の効果的な作り方とは?制作メリットや活用シーン、実際の事例も紹介

政府や自治体などの公的機関では、国民や地域住民のために健康や防災にまつわる啓蒙活動をおこなっています。
過去にはリーフレットなどの紙媒体で行われていた啓蒙活動ですが、昨今ではより理解を促すことが可能な動画媒体で資料を制作するケースが増えています。
今回は、啓蒙活動を動画媒体で行うメリットやその活用シーン~動画を制作する際のポイントについて詳しく解説していきます。
さいごに啓蒙動画制作事例もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
啓蒙動画とは?
「啓蒙動画」とは、環境問題や人権、健康、災害対策など、社会的に重要なテーマについての理解を深めることを目的とした映像コンテンツです。
複雑な内容でも、映像や音声を活用することで、視聴者にわかりやすく伝えることができるのが特徴です。
このような動画は、政府や自治体、企業、NPOなど、さまざまな団体によって制作されています。単に情報を届けるだけでなく、視聴者の意識を変え、行動を促すことが大きな目的です。
たとえば、地球温暖化の現状を伝える動画が、日常生活での省エネ行動につながるといった効果が期待されています。
■【環境局 こども環境局】考えてみよう!地球温暖化
また、「啓蒙」という言葉には「知識を与えて導く」という意味がありますが、やや一方的な印象を持たれることもあります。
そのため、最近では「気づきを促す」という意味合いを持つ「啓発」という言葉が、公的な場面ではより好まれる傾向にあります。
とはいえ、啓蒙動画は、社会課題を身近に感じさせ、私たち一人ひとりが「知ること」から「行動すること」へとつなげるための有効な手段です。
情報があふれる現代において、信頼できる知識をわかりやすく届けるツールとして、今後もその役割がますます重要になっていくでしょう。
啓蒙動画を制作するメリット
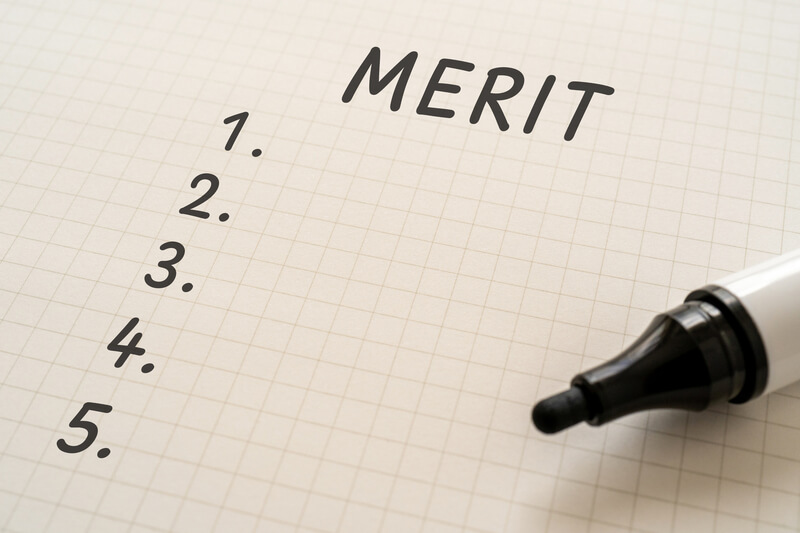
動画は、音と映像が組み合わさることで、テキストだけでは伝えきれない情報を効果的に届けることができます。ここでは、啓蒙動画を制作すべき理由について「4つの視点」からわかりやすく解説していきます。
- ●講義やテキストより記憶が定着しやすい
- ●複雑な情報も簡潔に伝えられる
- ●社会的な課題の理解促進につながる
- ●視聴者の行動変容を促せる
講義やテキストより記憶が定着しやすい
啓蒙動画の大きな魅力のひとつは、記憶への定着率が高いことです。
アメリカ国立訓練研究所の調査によると、テキストで学んだ場合の記憶定着率は約10%にとどまるのに対し、動画を通じて学んだ場合は約20%に向上するとされています。
映像と音声が組み合わさることで、視覚と聴覚の両方に訴えかけ、理解が深まりやすくなるのです。
さらに、視聴者に問いかけたり、考えさせたりするような工夫を動画に取り入れることで、記憶の定着率はさらに高まると考えられています。
単なる情報の受け取りにとどまらず、能動的な学びを促す点でも、啓蒙動画は非常に効果的な手段といえるでしょう。
複雑な情報も簡潔に伝えられる
啓蒙活動では、政治や科学、社会制度など、専門的で難解な情報を扱う場面が多くあります。
こうした複雑な内容も、映像と音を組み合わせた動画なら、わかりやすく伝えることができます。
たとえば、イラストや図解、グラフなどを活用すれば、抽象的な概念も具体的にイメージしやすくなり、視聴者の理解の助けになるでしょう。また、ナレーションや字幕を工夫することで、よりわかりやすくすることも可能です。
動画は、複雑なテーマを誰にでも伝えられる、非常に有効な手段と言えるでしょう。
社会的な課題の理解促進につながる
環境問題や貧困といった社会的課題は、日常の中では見過ごされがちです。
啓蒙動画は、そうした課題を視聴者に強く印象づける手段として注目されています。
感情に訴える映像表現によって、視聴者は問題の深刻さを自分のこととして受け止めるようになります。
例えば、破壊された自然や困窮する人々の姿を目にすることで、現実への共感が生まれ、理解が深まります。
■貧困が子どもたちから奪うもの /日本ユニセフ協会
その理解は、個人の意識を変えるだけでなく、社会全体の価値観や行動の変革にもつながっていくのです。
視聴者の行動変容を促せる
丁寧に制作された啓蒙動画は、視聴者の心に深く訴えかける力を持っています。
特に、専門家の意見や統計データを交えた構成は、情報の信頼性を高め、視聴者の納得感を生み出します。
さらに、動画内で具体的な行動例や実践方法(「マイバックを持参する」「家庭でできる節電方法」など)を提示することで、視聴者が「自分にもできる」と感じ、実際の行動へとつながる可能性が高まります。
啓蒙動画は、単なる情報提供にとどまらず、視聴者の意識を変え、社会的な課題解決に向けた一歩を踏み出させる強力なツールなのです。
啓蒙動画の活用シーン

啓蒙動画は下記に挙げるような様々な場面で活用されていますので、順番に解説していきます。
- ●安全教育による被害防止
- ●予防医学の普及
- ●環境活動などの紹介
- ●防災意識の醸成
安全教育による被害防止
私たちの身の回りには、交通事故や犯罪、機器の誤使用による事故など、さまざまな危険が潜んでいます。
こうしたリスクから身を守るために行われる安全教育の現場で、啓蒙動画は非常に効果的なツールとして活用されています。
動画は、実際に起こりうる危険なシチュエーションを視覚的に再現することで、視聴者に「自分ごと」として危機意識を持たせることができます。
たとえば、交通安全の啓蒙動画では、信号無視やスマートフォンのながら歩きが事故につながる様子をわかりやすく描き、ルールの重要性を伝えます。
また、スマートフォンや家電製品の正しい使い方を紹介する動画では、誤った使用による発火や感電といった事故を未然に防ぐことができます。
■自転車安全利用 ③歩きスマホの危険性
こうした動画は、子どもから高齢者まで幅広い世代に向けて、安全意識を高める手段として非常に有効です。
予防医学の普及
近年、病気の早期発見や生活習慣の改善を目的とした「予防医学」の重要性が高まっています。
その普及を支える手段として、啓蒙動画が大きな役割を果たしています。
特に、糖尿病や高血圧、がんなど、重くなりやすい疾患についての情報は、文章だけでは伝わりにくいこともありますが、動画ならアニメーションや図解を使って、親しみやすく、わかりやすく伝えることができます。
さらに、実際の患者の体験談や、医師のアドバイスを盛り込んだストーリー仕立ての動画は、視聴者の感情に訴えかけ、健康への意識を高めるきっかけになります。
啓蒙動画は、単なる知識の提供にとどまらず、健康意識の向上と行動変容を促す有効なツールとして、今後ますます活用が期待されています。
環境活動などの紹介
環境問題や人権課題など、社会的なテーマに対する企業の取り組みを伝える手段として、啓蒙動画は非常に効果的です。
たとえば、企業が行っている環境保護の取り組みを、動画を通じてわかりやすく紹介することで、社内外の理解を深めることができます。
特に、CO₂排出量の削減効果やリサイクル率といった具体的なデータを示しながら、個人でも実践できる行動を紹介することで、「自分にもできる」という意識を育み、行動変容へとつなげることが可能です。
■2050年カーボンニュートラルどうやって実現する?
また、こうした啓蒙動画は、顧客や従業員、取引先など、さまざまなステークホルダーに向けて企業の姿勢を伝えるうえでも、今後ますます活用の幅を広げていくでしょう。
防災意識の醸成
地震や台風、豪雨など、自然災害が多い日本において、防災意識の向上は地域社会にとって欠かせない課題です。
こうした中で、啓蒙動画は住民の防災意識を高める有効な手段として注目されています。
動画では、避難経路の確認や非常持ち出し品の準備、災害時の行動手順などを、実際の映像やアニメーションを交えてわかりやすく紹介できます。
特に、外国人居住者が多い地域では、多言語対応の動画を通じて防災情報を共有し、地域の訓練や自治体の取り組みと連携することで、住民の意識向上と被害の軽減が期待されます。
■【今こそ備えよう!動画で学ぶ令和の防災!】情報対策①防災情報の収集
啓蒙動画は、地域の安全を守るための「伝える力」として、今後ますます重要な役割を果たしていくでしょう。
啓蒙動画の効果的な作り方

啓蒙動画の効果を上げるために心がけたい6つのポイントについて詳しく紹介します。
これから動画制作を検討する方はぜひ参考にしてください。
- ●目的とターゲットを明確に設定する
- ●ストーリーや映像で感情に訴えかける
- ●情報の信ぴょう性を重視する
- ●わかりやすい表現を心がける
- ●被害者の心情に配慮する
- ●多角的な視点を提示する
目的とターゲットを明確に設定する
啓蒙動画を効果的に制作するためには、まず「何のために、誰に向けて伝えるのか」という目的とターゲットを明確に設定することが重要です。
これが曖昧なままだと、伝えたいメッセージがぼやけてしまい、視聴者の心に届きにくくなります。
たとえば、「20代の若者に二酸化炭素排出量削減の重要性を伝える」といったように、対象と目的を具体的に定めることで、動画の内容やトーン、構成、使用するビジュアルや言葉選びまで、すべての方針が自然と定まっていきます。
ターゲットが明確であればあるほど、視聴者の関心や行動に寄り添った表現が可能になり、動画の訴求力も高まります。
ストーリーや映像で感情に訴えかける
啓蒙動画で重要な情報を伝えるためには、まず視聴者に最後まで見てもらうことが不可欠です。
そのためには、印象的な映像や音、そして心に残るストーリー展開によって、視聴者を動画の世界に引き込む工夫が求められます。
たとえば、交通事故の再現映像を用いることで、視聴者に強い印象を与え、交通ルールの重要性を深く理解してもらうことができます。
こうした感情に訴える演出は、単なる情報伝達を超えて、視聴者の意識や行動に働きかける力を持っています。
また、登場人物の体験談や日常の中の気づきを描いたストーリーは、共感を生みやすく、視聴者が自分自身の生活に照らして考えるきっかけにもなります。
情報の信ぴょう性を重視する
啓蒙動画は、視聴者に正しい知識や意識を届けることが目的であるため、発信する情報の信ぴょう性が非常に重要です。
信頼性のある情報を用いることで、動画そのものの説得力が高まり、視聴者からの信頼も得やすくなります。
たとえば、政府機関やWHOなどの公的データや専門家のコメントに加え、実際にそのテーマに関わった人の体験談やインタビューを盛り込むことで、情報の裏付けが明確になり、視聴者の共感を呼びながら内容に深みを加えることができます。
このように、正確で信頼できる情報を丁寧に伝えることが、啓蒙動画の質を大きく左右するのです。
わかりやすい表現を心がける
啓蒙動画は、専門的で複雑な情報を一般の人々にわかりやすく伝えることを目的としているため、専門用語や難解な表現はできるだけ避け、かみ砕いた言葉で説明することが大切です。
視聴者の知識レベルを意識しながら、誰にでも伝わる表現を心がけることで、理解度が大きく変わってきます。
また、提示する情報は、内容を詰め込みすぎず、要点を整理して構成することが重要です。
図やイラスト、アニメーションなどを活用して視覚的に補足することで、情報がよりスムーズに伝わり、視聴者が自ら行動を起こすきっかけにもなります。
わかりやすさは、啓蒙動画の効果を左右する大きな要素です。伝える側の工夫次第で、難しいテーマも身近で理解しやすいものへと変わっていきます。
被害者の心情に配慮する
啓蒙動画では、いじめなど、センシティブなテーマを取り上げることも少なくありません。
こうした内容を扱う際には、被害者の心情に十分な配慮をすることが非常に重要です。
動画を視聴した際に、過去の体験を思い出して苦しむ可能性があることを念頭に置き、表現方法には慎重さが求められます。
特に事件や事故の再現映像はインパクトが強く、被害者に精神的負担を与える可能があるため、詳細な描写は避け、事実の伝達と心のケアのバランスを意識することが望まれます。
啓蒙動画は、社会的な課題を伝える力を持っていますが、その影響力が大きいからこそ、誰かを傷つけないための配慮が欠かせません。
多角的な視点を提示する
啓蒙動画では、環境問題や社会的な課題など、複雑で多面的なテーマを扱うことが少なくありません。
こうしたテーマを伝える際は、特定の立場に偏らず多角的な視点を提示することで、偏見を排除し、公平で深みのある理解を促すことが大切です。
たとえば、年齢や文化的背景、職業などが異なる複数の人々の意見や体験を取り入れることで、テーマに対する多様な見方を紹介できます。
これにより、視聴者は自分とは異なる立場にも目を向けるようになり、包括的な理解につながります。
啓蒙動画は、ただ情報を伝えるだけでなく、視聴者の視野を広げる役割も担っているのです。
啓蒙動画の制作事例

さいごに、啓蒙動画の具体的な制作事例を3つ紹介しますので参考にしてみてください。
石坂産業株式会社様/事業紹介映像
「廃棄物処理=汚い」という先入観を覆す、事業紹介型の啓蒙動画です。
美しい自然と調和する施設の映像に、機械音や風の音を織り交ぜ、処理されたウッドチップが土となり、野菜を育て、人へと循環する姿を描きます。環境と食育の視点から、廃棄物処理の価値を再定義するメッセージ性の深い作品です。
日榮新化株式会社様/プロジェクトPR映像
「資源循環プロジェクト」は、廃棄されていた剥離紙をリサイクル可能な専用台紙に置き換えることで、資源の循環とCO₂削減を目指す取り組みです。
本啓蒙動画では、まずゴミが大量に生まれている現実を提示し、視聴者に問題意識を促した上で、このプロジェクトを解決策として紹介。視聴後にプロジェクトへの共感や好感を自然と抱いてもらえるよう、感情に訴える演出が随所に施されており、環境問題という重いテーマを親しみやすく、かつ印象深く伝える映像表現が高く評価されています。
日本エックス線検査株式会社様/事業紹介映像
こちらは、非破壊検査の社会的意義を伝える啓蒙動画です。
非破壊検査とは、構造物を壊すことなく内部の状態を確認し、事故を未然に防ぐ技術。普段は目立たないながらも、社会の安全を支える重要な仕事です。
この啓蒙動画では、「見えない貢献」に焦点を当て、非破壊検査の価値を広く伝えることを目指しました。BGMやカットごとの演出にもこだわり、視聴後には共感や敬意が自然と生まれる構成に。社会貢献性を感情に訴える映像表現が特徴です。
まとめ
今回は啓蒙動画について紹介しましたがいかがでしたでしょうか。
啓蒙動画において重要なポイントは、対象となるターゲット層をよく考えてわかりやすい演出をするということです。商用の動画広告にも通じる部分ではありますが、啓蒙動画の場合にはより一層、視聴者の心情に寄り添う演出上の工夫が必要と言えます。
啓蒙動画を制作する際には、是非上記のポイントにも注意を払ってアイデアを練ってみてください。
初めての映像制作の方にも、ご不安なくご利用いただけるよう制作の流れやご活用方法まで、
丁寧にご案内させていただきます。お客様の映像制作のゴールを達成するため、
企画〜撮影、完成まで専任チームが伴走いたします。