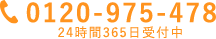映像制作・動画制作のコラム
2025年4月1日
テレビCMの効果測定が重要な理由とは?成果を出す効果測定方法を解説

テレビCMは、幅広い視聴者にリーチできる強力な広告手段です。しかし、その効果を正確に把握しなければ、本当に成果を上げているのか判断することはできません。
本記事では、テレビCMの効果測定の重要性や成果を出す測定方法について紹介します。テレビCMで効果を上げるポイントについても解説していますので、テレビCMの効果測定で成果を出したい方は、参考にしてください。
目次
テレビCMの効果測定を行なう重要性

テレビCMの効果測定は、広告戦略を成功させる手段の一つとして極めて重要な役割を果たしています。効果測定によって視聴者の反応や行動変化を詳細に分析できれば、今後の制作に活かせるさまざまな洞察が得られます。
また、予算組みをするうえでも、効果測定は重要です。無駄のない予算配分をするには、各テレビCMの影響をできるだけ正確に把握する必要があります。さらに、効果測定で具体的な数値として費用対効果を示せれば、経営陣や関係者に対して説得力のある報告をすることができます。
継続的な効果測定によって、長期的なブランド価値の向上や売上への貢献度も明確になり、広告活動の重要性を裏づけられるでしょう。
テレビCMの効果測定は難しい?

テレビCMの効果測定は、以前から広告主にとって大きな課題でした。テレビCMはインターネット広告と異なり、視聴後の態度変容の把握や購買行動との因果関係の特定が難しいためです。さらに、テレビCMは即時的な効果よりも、長期的なブランド認知や好感度の向上を想定するケースが大半で、長期間の効果測定が必要です。
しかし、近年はテクノロジーの進歩により、テレビCMの効果測定手段も増えています。クロスチャネル分析やビッグデータの活用、AIを用いた分析ツールなど、より精緻な効果測定が可能になりつつあるのです。
TVCMにおいて効果的な広告戦略を立案するためには、これらの新しい手法を積極的に取り入れていくことが欠かせません。
テレビCMの効果測定に用いる代表的な手法

テレビCMの効果測定方法は複数ありますが、測定精度を高めるにはそれぞれの特徴をよく理解し、適切に活用することが重要です。
ここでは、代表的な効果測定方法を6つ解説します。
GRPの算出
GRP(Gross Rating Point)は、一定期間に放送されたCMの世帯視聴率を合計した数値で、「延べ視聴率」とも呼ばれます。GRPは以下の計算式で算出し、数値が大きいほど多くの視聴者の目に触れたテレビCMであるいえます。
GRP=視聴率×CMの放送回数
例えば、視聴率5%のCMを10回放送した場合は、50GRPです。
ただし、世帯視聴率をベースにするため、個人への到達度を正確に測るのは困難です。
また、視聴者が実際にCMを見ているかどうかも判断することはできません。そのため、GRPとほかの方法を組合せた、総合的な判断が必要です。
GAP
GAP(Gross Attention Point)は、センサーカメラなどを用いて、視聴者がテレビCMにどれだけ注目しているかを測定する方法です。視聴者が1秒間テレビCMを注視した場合を「1GAP」とするように、秒単位で計測できます。
GAPのメリットは、「視聴者が対象のテレビCMに興味を持っているか」を、実数で測定できる点です。よってテレビCMの内容や構成がどの程度視聴者の関心を引きつけているかを客観的に評価できます。
一方で、GAPは実証実験が開始されてから日が浅く、効果測定方法として信頼しうる段階にあるとは言い切れません。
今後の発展が期待される一方、現時点ではGRPやほかの方法と組合せて活用する必要があるでしょう。
クロスチャネル分析
クロスチャネル分析は、ほかの広告チャネルの動向を通して、テレビCMが消費者行動に与える影響を総合的に評価する方法です。
テレビCMの放送後、オンライン広告のクリック数やSNSのフォロワー数など、ほかの広告チャネルに動きがあったかを追跡することで、より詳細な効果測定ができます。
また、テレビCMがほかの広告と組合さった際のシナジー効果の把握や、各広告チャネル自体の効果測定も可能です。
ただしクロスチャネル分析を実施する場合は、データの管理環境や運用ルールといった社内整備が不可欠です。適切なペルソナ設定とデータ分析が必要なため、周到な準備や計画が欠かせません。
アンケート
アンケートは、テレビCMの効果を直接的に測定する方法の一つです。視聴者にCMに関するアンケート調査を行なうことで、ブランド認知度や好感度、購買意欲などの変化を把握できます。
また、GRPやGAPでは捉えきれない視聴者のリアルな声を聞けるため、ブランドに対するイメージやCMの具体的な影響を知りたい場合に適しています。
一方、アンケート調査は、ターゲットの明確化や定期的な実施が必要です。また、回答の精度を高めるためにも、思い込みを避け、視聴者の意見を引き出す質問の作成が重要です。
アナリティクスやその他分析ツールの活用
効果測定では、テレビCMの効果をより詳細に分析できるアナリティクスツールやサービスも多く用いられます。
これらのツールやサービスによって、視聴率データの収集や消費者行動の追跡、オンラインとオフラインデータの統合的な分析など、さまざまな切り口から効果を測ることが可能です。
また、テレビCM放送後のWebサイト閲覧数の変化やSNSでの反応数なども即時に把握できます。例えばGoogleアナリティクスでは、AIを活用した高度な予測分析も可能です。
しかし、適切なツールの選択と運用には、専門的な知識やスキルを持った人材が欠かせません。
さらに、ツールによって分析できるデータの種類や精度が異なるので、複数のツールを組合せるような工夫も必要です。
A/Bテスト
A/Bテストは、放送する地域や時間帯、テレビCMの内容など、条件変化による効果の違いを検証する方法です。
この方法は、繰り返すことで検証精度が上がり、ターゲット層へリーチしやすい放送条件を効率的に見つけられます。
A/Bテストを実施する際は、比較する要素を1つに絞り、同一条件下で検証することが重要です。複数の要素を同時に変更すると、どの要素が結果に影響したのか判断しにくくなるので注意しましょう。
なお、ローカルエリアでのテスト放送を通じて、最適な時間帯や番組を見極めてから全国放送することで、コスト面のリスクを軽減することが可能です。
テレビCMの効果を上げる5つのポイント

テレビCMは強力な広告手段ですが、効果を最大化するには戦略的なアプローチが必要です。ここでは、テレビCMの成果を出すために重要な5つのポイントを解説します。
ターゲット層の明確化
テレビCMの効果を最大化するには、目的や訴求したい商品・サービスに合わせたターゲット層の絞り込みが重要です。
年齢や性別、ライフスタイルなどのさまざまな視点から、ターゲット層がよく視聴する番組や時間帯を選定することで、リーチの精度を高められます。
ただし、ターゲットの設定は柔軟に考えることが大切です。例えば、小学生向け商品のCMを制作する場合、実際の購買者である親の視点も考慮する必要があります。
ターゲット層を明確にすることで適した時間帯や番組を想定でき、予算内で効率的にリーチすることが可能になります。
クリエイティブなコンテンツ作成
広告効果の高いテレビCMにするには、視聴者の記憶に残りやすい、インパクトのあるコンテンツにすることが重要です。
シンプルでわかりやすいメッセージやキャッチーな音楽、視覚的に訴える映像を活用することで、商品やブランドの認知度を高められるでしょう。
関連記事:【7ステップ】CM制作の流れや必要費用の相場や内訳について詳しく解説
複数の広告チャネルと連携
テレビCMの効果を最大化するには、Web広告やSNSなど、ほかのチャネルと連携したクロスメディア戦略を展開すると効果的です。
具体的な事例としては、自動車メーカーの新車発売キャンペーンが挙げられます。
テレビCMで大々的に告知し、同時にWeb広告やSNSで詳細な情報を提供することで、多様な消費者層へリーチできます。
また、テレビCMで紹介したキャンペーンサイトへの誘導や、テレビCMで使用したハッシュタグをSNSで拡散させるなど、オンラインとオフラインの連携も有効です。
複数の広告チャネルと連携したテレビCMは、視聴者との接点を増やせるため、各メディアの特性を活かした相乗効果が期待できます。
費用対効果を考慮した放送時間帯番組の選定
テレビCMは、時間帯や曜日によって放送費用が大きく変動します。不要なコストをかけないためにも、ターゲット層に合わせた時間帯や番組の選定が重要です。
例えば、30〜40代の会社員がターゲットの場合、通勤前後に視聴される可能性が高いと予想できます。
よって、平日の朝や夜の時間帯にテレビCMを放送すると、効果的にリーチできるでしょう。
そのほか、子育て中の親がターゲットの場合、教育番組やファミリー向け番組でテレビCMを放送するのが有効です。
また、特定の番組とのタイアップや、視聴率の高い番組の前後に放送するなど、戦略的な配置も検討する必要があります。
ただし、高視聴率の時間帯は費用も高いため、予算とのバランスを考えて放送枠を検討しましょう。
効果測定と改善のサイクル
テレビCMの放送後には、目的に合った効果測定を実施し、データに基づいた改善を行ないましょう。
視聴率だけでなく、Webサイトへのアクセス数や問い合わせ件数の変化、売上の推移など、多角的に効果を分析する必要があります。
分析の結果、テレビCMの効果が薄いと判断された場合は、放送のタイミングや内容を見直し、次回の戦略に活かすことが大切です。
逆に、特定の時間帯で反応が良かった場合は、その時間帯に集中してCMを放送するように調整するとよいでしょう。
このように、テレビCMの効果を着実に高めるには、効果測定と改善のサイクルを継続的に回していくことが大切です。
常にデータを収集・分析し、戦略を柔軟に調整することで、長期的な成功にもつながるでしょう。
進化するテレビCMの効果測定技術

テレビCMの効果測定技術は、データ分析やテクノロジーの進化により、大きく進歩しています。
新たな測定方法やツールの誕生、リアルタイムの効果測定の普及、スマートテレビによるIoT技術の進化などです。視聴データの取得方法は多様化しており、近年ではより詳細な分析が可能です。
とりわけ、AIや機械学習の活用は、効果測定の精度を飛躍的に向上させています。
例えば、株式会社野村総合研究所が開発した予測モデルでは、約3万サンプルのシングルソースデータをAIで解析。CM認知スコアを95.3%、購入・利用意向スコアを91.3%の精度で予測することに成功しました。
技術の進歩により、テレビCMとデジタル広告との境界は今後ますます曖昧になると予想されています。広告主にとって、今後さらに価値のある効果測定方法の登場が期待されます。
まとめ
テレビCMの効果測定は、広告投資の成果を最大化するためには切っても切り離せないものです。
本記事では、多角的なアプローチができる6種類の効果測定方法を紹介しました。紹介した測定方法のなかから、自社に合った方法を選定してみましょう。
効果測定後は結果をもとに適切な改善を行ない、テレビCMの効果を高めていくことが大切です。
Shibuya Movieでは、企画から構成、撮影、納品までワンストップでのテレビCM制作をご提供しています。広告効果の高いテレビCM制作をご希望の方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。